みなさん、こんにちは!
今回は2025年4月の最新データをもとにQYLDとXYLDを徹底比較!初心者の方にも分かりやすく、以下のポイントを深掘りしていきます。
・セクター比率
・構成銘柄比率
・過去の株価推移
・S&P500との比較
・配当/利回り/増配率/過去と将来のYOCシミュレーション
・月10万円配当受取に必要な投資額
・トータルリターン(累積・年率)/リスク分析
・過去投資をしていた場合のシミュレーション(一括・積立)
この記事を読めば、QYLDとXYLDの本当の姿が見えてきて、あなたの投資判断にきっと役立つはずです。さあ、一緒にこの魅力とリスクに満ちたETFの世界を探求していきましょう!
QYLDとXYLDの組入銘柄比率:どんな会社に投資しているの?
まずは、QYLDとXYLDがどんな会社の株に投資しているのか、その中身を見ていきましょう。

QYLD 上位10銘柄 (2025/04時点)
| 企業名 | 比率 |
|---|---|
| APPLE INC | 8.75% |
| MICROSOFT CORP | 8.27% |
| NVIDIA CORP | 7.89% |
| AMAZON.COM INC | 5.49% |
| BROADCOM INC | 4.00% |
| META PLATFORMS INC | 3.29% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3.08% |
| NETFLIX INC | 2.96% |
| TESLA INC | 2.66% |
| ALPHABET INC-CL A | 2.63% |
| その他 | 41.62% |
| 合計 | 100.00% |
XYLD 上位10銘柄 (2025/04時点)
| 企業名 | 比率 |
|---|---|
| APPLE INC | 6.64% |
| MICROSOFT CORP | 6.27% |
| NVIDIA CORP | 6.00% |
| AMAZON.COM INC | 3.70% |
| META PLATFORMS INC | 2.50% |
| BERKSHIRE HATH-B | 2.12% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.99% |
| BROADCOM INC | 1.83% |
| ALPHABET INC-CL C | 1.64% |
| TESLA INC | 1.55% |
| その他 | 59.60% |
| 合計 | 100.00% |
構成銘柄の傾向と特徴
- QYLDは、ナスダック100指数に連動するETFで、Apple、Microsoft、NVIDIAといった大型ハイテク株の比率が非常に高いのが特徴です。「その他」の比率も比較的低く、上位銘柄への集中度が高いと言えます。
- XYLDは、S&P500指数に連動するETFです。こちらもAppleやMicrosoftなどのハイテク株が上位を占めますが、QYLDほどではありません。ウォーレン・バフェット率いるBerkshire HathawayやJPMorgan Chase(その他に含まれる)など、金融セクターの銘柄も含まれており、QYLDよりは分散が効いていると言えるでしょう。「その他」の比率が約60%と高く、より多くの銘柄に投資していることがわかります。
どちらも米国の主要企業に投資していますが、QYLDはハイテク株中心、XYLDはより幅広い業種に分散している、という違いがありますね。
QYLDとXYLDのセクター比率:どの分野に強いの?
次に、投資先の業種(セクター)の比率を見てみましょう。これにより、それぞれのETFがどのような経済状況で値上がり・値下がりしやすいかの傾向が見えてきます。

QYLD セクター比率 (2025/04時点)
| セクター名 | 比率 |
|---|---|
| Technology | 51.41% |
| Communication Services | 15.71% |
| Consumer Cyclical | 12.69% |
| Consumer Defensive | 6.40% |
| Healthcare | 6.35% |
| Industrials | 3.42% |
| Basic Materials | 1.54% |
| Utilities | 1.32% |
| Financial Services | 0.51% |
| Energy | 0.45% |
| Real Estate | 0.21% |
| 合計 | 100.00% |
XYLD セクター比率 (2025/04時点)
| セクター名 | 比率 |
|---|---|
| Technology | 32.06% |
| Financial Services | 12.78% |
| Healthcare | 12.09% |
| Consumer Cyclical | 10.23% |
| Communication Services | 8.83% |
| Industrials | 7.53% |
| Consumer Defensive | 6.06% |
| Energy | 3.39% |
| Utilities | 2.62% |
| Real Estate | 2.43% |
| Basic Materials | 1.98% |
| 合計 | 100.00% |
セクター構成の特徴と値動きの傾向
- QYLDは、テクノロジーセクターが半分以上を占めており、非常に偏った構成です。次いで通信サービス、一般消費財と続きます。
- 値上がりしやすい時: テクノロジー株が市場を牽引するような、強い成長相場(ただし、カバードコール戦略のため上昇幅は限定的)。
- 値下がりしやすい時: 金利上昇局面や景気後退懸念などでハイテク株が売られる時。セクターが偏っているため、テクノロジーセクター全体の不調の影響を大きく受けやすいです。
- XYLDは、テクノロジーセクターの比率も高いですが、QYLDほどではありません。金融、ヘルスケア、一般消費財、通信サービス、資本財など、より多くのセクターに分散されています。
- 値上がりしやすい時: 景気拡大局面で幅広いセクターが上昇する時(こちらも上昇幅は限定的)。
- 値下がりしやすい時: 市場全体が下落する局面。ただし、QYLDよりは分散されているため、特定のセクターの不調による影響は相対的に小さい可能性があります。
セクター構成からも、QYLDはハイテクセクターの動向に、XYLDはより市場全体の動向に影響を受けやすいことがわかりますね。
QYLDとXYLDの過去10年の株価チャートと分析:値動きはどうだった?
ETFの価格(株価)が過去どのように動いてきたかを見てみましょう。カバードコール戦略特有の値動きに注目です。

過去10年の変動率 (2015/04/27基準)
| 銘柄 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2025/04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | -2.57% | -5.77% | 4.34% | -10.20% | 0.04% | -4.38% | -6.07% | -33.16% | -27.39% | -23.35% | -34.09% |
| XYLD | -5.92% | -0.67% | 10.79% | -3.28% | 11.24% | 0.39% | 10.37% | -14.33% | -14.20% | -9.11% | -19.57% |
チャートから読み取れる情報と傾向
チャートを見ると、残念ながらQYLDもXYLDも長期的には株価が下落傾向にあることがわかります。これは、カバードコール戦略の「株価上昇による利益(キャピタルゲイン)を放棄する代わりに、オプションプレミアム収入(インカムゲイン)を得る」という特性によるものです。
- QYLDは、特に2022年以降のハイテク株下落の影響を強く受け、大幅に株価を下げています。ナスダック100指数自体が大きく上昇しても、その恩恵を受けられず、逆に下落局面では指数と同様に(あるいはそれ以上に)下落するリスクがあります。
- XYLDは、QYLDよりは下落幅が小さいものの、S&P500が長期的に上昇してきたことを考えると、株価の上昇はほとんど期待できません。
これらのETFは、株価の値上がり益(キャピタルゲイン)を狙うのではなく、あくまで毎月の分配金(インカムゲイン)を重視する投資家向けと言えます。
QYLDとXYLDのS&P500過去1年分チャートとの比較と分析:市場平均と比べてどう?
次に、より身近な市場の動きを示すS&P500指数(^GSPC)と、過去1年間のパフォーマンスを比較してみましょう。

パフォーマンス比較 (2024/05/01 - 2025/04/21)
| 銘柄 | 1ヶ月リターン | 3ヶ月リターン | 6ヶ月リターン | 1年リターン (近似) |
|---|---|---|---|---|
| QYLD | -2.90% | 2.03% | 4.88% | -9.18% |
| XYLD | -0.40% | 3.86% | 3.40% | -6.78% |
| ^GSPC | 12.42% | 16.75% | 14.33% | 2.95% |
| (注: 1年リターンは期間中の最終日のデータを使用) |
S&P500との比較からわかること
過去1年のチャートを見ると、S&P500が上昇傾向にあったのに対し、QYLDとXYLDのパフォーマンスは著しく劣っています。
- QYLDに至っては、トータルリターンがマイナスとなっており、受け取った分配金以上に株価が下落したことを意味します。
- XYLDもプラスではありますが、S&P500のパフォーマンスには遠く及びません。
これは、カバードコール戦略が市場の上昇局面では利益が限定されるというデメリットが顕著に表れた結果と言えます。市場が大きく上昇する場面では、これらのETFは取り残されやすいのです。
QYLD/XYLDで配当金生活はできる?配当金の分析
QYLDとXYLDの最大の魅力は、なんと言っても高い分配金利回りです。ここでは、その配当金(分配金)について詳しく見ていきましょう。
QYLD/XYLDの過去の配当金と増配率、その分析
毎月支払われる分配金は、投資家にとって嬉しい収入源ですよね。過去の推移はどうだったのでしょうか?

年間配当金合計と増配率
| 銘柄 | 年 | 分配金合計 | 増配率 |
|---|---|---|---|
| QYLD | 2016 | 2.04 | - |
| QYLD | 2017 | 1.89 | -7.7% |
| QYLD | 2018 | 2.65 | 40.6% |
| QYLD | 2019 | 2.32 | -12.4% |
| QYLD | 2020 | 2.54 | 9.6% |
| QYLD | 2021 | 2.85 | 12.0% |
| QYLD | 2022 | 2.19 | -23.2% |
| QYLD | 2023 | 2.04 | -6.7% |
| QYLD | 2024 | 2.34 | 14.7% |
| QYLD | 2025 | 0.68 | -11.5% (*1) |
| XYLD | 2016 | 1.38 | - |
| XYLD | 2017 | 2.60 | 88.4% |
| XYLD | 2018 | 3.15 | 21.2% |
| XYLD | 2019 | 2.92 | -7.5% |
| XYLD | 2020 | 3.68 | 26.2% |
| XYLD | 2021 | 4.58 | 24.5% |
| XYLD | 2022 | 5.29 | 15.4% |
| XYLD | 2023 | 4.15 | -21.6% |
| XYLD | 2024 | 4.84 | 16.7% |
| XYLD | 2025 | 1.44 | 12.8% (*1) |
配当金の推移と分析
グラフや表を見ると、QYLDもXYLDも年間の分配金合計額が安定していないことがわかります。増配する年もあれば、20%以上も減配する年もあります。
これは、カバードコール戦略で得られるオプションプレミアム収入が、市場のボラティリティ(変動の大きさ)に左右されるためです。市場が安定しているとプレミアム収入は減少し、逆に市場が不安定だと増加する傾向があります。
また、株価自体が下落傾向にあるため、将来的に分配金の原資が減少し、減配が続くリスクも考慮する必要があります。いわゆる「タコ足配当」(元本を取り崩して配当に回すこと)になっていないか、注意が必要です。
QYLD/XYLDの配当金を前月比で比較
毎月分配型のETFなので、月ごとの変動も見てみましょう。

配当金の前月比較 (2025年)
| 銘柄 | 年月 | 分配金合計 | 増配率 |
|---|---|---|---|
| QYLD | 2025-03 | 0.17 | - |
| QYLD | 2025-04 | 0.16 | -6.2% |
| XYLD | 2025-03 | 0.40 | - |
| XYLD | 2025-04 | 0.38 | -5.8% |
前月比での分析
直近のデータを見ると、QYLDもXYLDも前月と比較して分配金が減少しています。このように、月単位で見ても分配金額は変動します。
毎月分配は魅力的ですが、その金額が毎月一定ではない点は理解しておく必要があります。生活費などを分配金で賄おうと考えている場合は、変動リスクを考慮した計画が必要です。
QYLD/XYLDの配当金を前年同月比で比較
より長期的な傾向を見るために、前年の同じ月と比較してみましょう。

配当金の前年同月比較
| 銘柄 | 年月 | 分配金合計 | 増配率 |
|---|---|---|---|
| QYLD | 2024-04 | 0.17 | - |
| QYLD | 2025-04 | 0.16 | -7.3% |
| XYLD | 2024-04 | 0.34 | - |
| XYLD | 2025-04 | 0.38 | 10.9% |
前年同月比での分析
2025年4月の分配金を見ると、QYLDは前年同月比でマイナス(減配)となっています。一方、XYLDはプラス(増配)です。
このように、同じカバードコール戦略でも、対象とする指数や市場環境によって分配金の動向は異なります。XYLDの方がS&P500を対象としており、ボラティリティがナスダック100より低い傾向があるため、分配金の変動も相対的にマイルドになる可能性がありますが、一概には言えません。
QYLD/XYLDの配当金利回りの推移
投資額に対してどれくらいの分配金が受け取れるかを示す「配当金利回り」。QYLD/XYLDの利回りはどのように推移してきたのでしょうか?

配当金利回りの分析
QYLDとXYLDは、常に高い配当金利回りを維持していることが最大の魅力です。多くの場合、10%を超える利回りとなっており、一般的な株式やETFと比較して非常に高い水準です。
しかし、注意点もあります。利回りは「年間配当金 ÷ 株価」で計算されるため、株価が下落すれば、配当金額が変わらなくても利回りは上昇します。
過去のチャートで見たように、QYLD/XYLDは株価が下落傾向にあるため、現在の高利回りが株価の下落によって支えられている(高く見えている)可能性があります。
利回りの高さだけに注目せず、株価の動向やトータルリターン(株価変動+配当金)で判断することが重要です。
過去QYLD/XYLDに投資していた場合のYOCシミュレーション
YOC(Yield on Cost)とは、取得時の株価に対する現在の配当利回りのことです。もし過去にQYLDやXYLDに投資していたら、現在のYOCはどうなっているでしょうか?

過去購入した場合のYOC推移 (%)
| 銘柄 | 2015年末 | 2017年末 | 2019年末 | 2021年末 | 2023年末 | 2025年4月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 10.36 | 9.89 | 10.27 | 10.93 | 13.99 | 15.51 |
| XYLD | 12.20 | 10.62 | 10.54 | 10.57 | 13.54 | 14.44 |
YOCシミュレーションの解説
YOC(Yield on Cost)は、あなたが投資した元本に対して、現在どれくらいの配当利回りになっているかを示す指標です。
シミュレーション結果を見ると、QYLDもXYLDも、過去に投資していた場合、現在10%を超える非常に高いYOCになっていることがわかります。例えば、2015年末にQYLDに100万円投資していた場合、2025年4月時点のYOCは約15.51%となり、年間約15.5万円の分配金を受け取っている計算になります(税引前)。
これは、株価は下がったものの、分配金が(株価ほどは)下がらなかった(あるいは一時的に増えた時期もあった)ため、取得価格に対する利回りが上昇したことを意味します。
ただし、これはあくまで「取得価格に対する利回り」です。YOCが高くても、現在の株価が取得価格を下回っていれば、売却すると損失(元本割れ)が発生します。高YOCは魅力的ですが、含み損を抱えている可能性が高い点には注意が必要です。
QYLD/XYLDの将来のYOC予想シミュレーション
では、仮に現在の株価下落率や利回りが続いた場合、将来のYOCはどうなると予想されるでしょうか?

将来YOC予想 (%)
| 銘柄 | 2025 | 2027 | 2029 | 2031 | 2033 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 14.41 | 13.26 | 12.19 | 11.22 | 10.32 | 9.49 |
| XYLD | 13.52 | 12.94 | 12.39 | 11.86 | 11.35 | 10.87 |
将来YOC予想の解説
過去の株価と配当金の傾向(特に株価の下落傾向)が今後も続くと仮定して、将来のYOCをシミュレーションしてみました。
- QYLD:現在(2025年)100万円投資すると、初年度のYOCは約14.41%(年間約14.4万円の分配金)ですが、10年後の2035年にはYOCは約9.49%まで低下すると予想されます。
- XYLD:同様に、現在100万円投資すると、初年度YOCは約13.52%(年間約13.5万円)、10年後の2035年にはYOCは約10.87%まで低下すると予想されます。
どちらも10年後でも比較的高水準のYOCを維持する可能性はありますが、株価の下落が続けば、YOCも徐々に低下していく可能性が高いことを示唆しています。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、将来の配当金の支払いや成長を保証するものではないため注意が必要です。
QYLD/XYLDで配当金生活をするには?QYLD/XYLDの配当金受取シミュレーション
配当金生活をするには?配当金による不労所得でFIREはできる?
毎月の配当受取目標と必要な投資額のシミュレーション ※日次更新
(毎月10万円配当を受け取るために必要な投資額)
| 銘柄 | 株価 | 配当利回り | 月間配当目標 | 必要投資額 | 必要投資額 (課税考慮) |
必要株数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | $17.81 (¥2,742) |
11.41% | ¥10,000 | ¥1,051,979 | ¥1,466,857 | 535株 |
| ¥30,000 | ¥3,155,936 | ¥4,400,572 | 1,605株 | |||
| ¥50,000 | ¥5,259,894 | ¥7,334,287 | 2,675株 | |||
| ¥100,000 | ¥10,519,787 | ¥14,668,573 | 5,350株 | |||
| XYLD | $40.73 (¥6,271) |
10.45% | ¥10,000 | ¥1,147,998 | ¥1,600,744 | 256株 |
| ¥30,000 | ¥3,443,993 | ¥4,802,232 | 766株 | |||
| ¥50,000 | ¥5,739,988 | ¥8,003,721 | 1,277株 | |||
| ¥100,000 | ¥11,479,977 | ¥16,007,441 | 2,553株 |
為替レート: 153.97円/ドル
QYLD/XYLDの権利落ち日、配当情報
QYLDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-23 | 0.18 |
| 2025-12-22 | 2025-12-30 | 0.18 |
| 2025-11-24 | 2025-12-02 | 0.17 |
| 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0.17 |
| 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.17 |
| 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0.17 |
| 2025-07-21 | 2025-07-28 | 0.17 |
| 2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.17 |
| 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.17 |
| 2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.16 |
| 2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.17 |
| 2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.17 |
XYLDの配当情報
| 権利落ち日 | 現地配当支払日 | 配当額 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 2026-01-23 | 0.36 |
| 2025-12-22 | 2025-12-30 | 0.33 |
| 2025-11-24 | 2025-12-02 | 0.40 |
| 2025-10-20 | 2025-10-27 | 0.40 |
| 2025-09-22 | 2025-09-29 | 0.30 |
| 2025-08-18 | 2025-08-25 | 0.32 |
| 2025-07-21 | 2025-07-28 | 0.31 |
| 2025-06-23 | 2025-06-30 | 0.39 |
| 2025-05-19 | 2025-05-27 | 0.39 |
| 2025-04-21 | 2025-04-28 | 0.38 |
| 2025-03-24 | 2025-03-31 | 0.40 |
| 2025-02-24 | 2025-03-03 | 0.29 |
6. QYLD/XYLDへ過去に投資していた場合の累積トータルリターン

累積トータルリターンデータ
| 銘柄 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン | 7年リターン | 10年リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 4.1% | 13.7% | 48.5% | 49.6% | 98.7% |
| XYLD | 6.1% | 8.0% | 59.6% | 46.1% | 78.8% |
累積トータルリターンの解説
過去にQYLDやXYLDに投資していた場合、どれくらいのリターンが得られたかを累積で見てみましょう。「トータルリターン」とは、株価の値上がり(または値下がり)に加えて、受け取った配当金(分配金)も考慮した総合的なリターンのことです。
- 10年間のリターンを見ると、QYLDは約98.7%、XYLDは約78.8%と、QYLDの方が高いリターンを上げています。これは、投資元本が約2倍近くになったことを意味します。
- しかし、期間を短くして見ていくと様相が変わります。
- 5年リターンでは、XYLDが59.6%と、QYLDの48.5%を上回っています。
- 3年リターンでは、QYLDが13.7%とXYLDの8.0%を上回りますが、その差は縮まります。
- 直近1年では、XYLDが6.1%と、QYLDの4.1%より良い結果となっています。
このように、投資する期間によって、どちらのETFが優位だったかは異なります。特にここ数年は、XYLDの方が相対的に良いパフォーマンスを示す場面が多いようです。ただし、どちらも市場平均(例えばS&P500)と比較すると、上昇局面でのリターンは見劣りする傾向がある点には注意が必要です。
QYLD/XYLDへ過去に投資していた場合の年率(CAGR)トータルリターン

年率(CAGR)トータルリターンデータ
| 銘柄 | 1年リターン | 3年リターン | 5年リターン | 7年リターン | 10年リターン |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 4.1% | 4.4% | 8.2% | 5.9% | 7.1% |
| XYLD | 6.1% | 2.6% | 9.8% | 5.6% | 6.0% |
年率(CAGR)トータルリターンの解説
次に、過去のトータルリターンを年率(CAGR: Compound Annual Growth Rate、年平均成長率)で見てみましょう。これは、投資期間中の平均的な1年あたりのリターンを示しており、異なる期間のリターンを比較しやすくする指標です。
- 10年間の年率リターンでは、QYLDが7.1%、XYLDが6.0%と、QYLDが優位です。毎年平均してこれくらいのリターンがあったと考えることができます。
- 5年間の年率リターンでは、XYLDが9.8%と、QYLDの8.2%を上回っています。この期間においては、XYLDの方が効率的に資産を増やせたことになります。
- 3年間の年率リターンを見ると、XYLDは2.6%とかなり低い水準になっています。QYLDも4.4%と、他の期間に比べて見劣りします。これは、ここ数年の株価低迷(特に2022年)の影響が大きいと考えられます。
- 直近1年では、XYLDが6.1%、QYLDが4.1%のリターンです。
年率リターンで見ても、投資期間によってパフォーマンスは変動します。特に近年のリターンは低迷気味であり、高配当の裏側にある株価変動リスクを考慮する必要があります。長期的に見ればプラスのリターンを出していますが、安定して高いリターンを期待するのは難しいかもしれません。
QYLD/XYLDへ10年前に100万円一括投資していた場合のシミュレーション

10年間の一括投資シミュレーション結果
| 銘柄 | 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 2016 | 95.5 | 8.7 | 104.2 | 104.2 |
| 2017 | 104.8 | 8.1 | 121.6 | 123.2 | |
| 2018 | 91.0 | 11.3 | 119.1 | 120.3 | |
| 2019 | 100.9 | 9.9 | 138.9 | 146.4 | |
| 2020 | 97.4 | 10.9 | 146.3 | 157.1 | |
| 2021 | 94.8 | 12.2 | 155.9 | 172.6 | |
| 2022 | 68.0 | 9.3 | 138.4 | 140.8 | |
| 2023 | 74.1 | 8.7 | 153.2 | 171.5 | |
| 2024 | 77.8 | 10.0 | 167.0 | 203.3 | |
| 2025 | 66.8 | 2.9 | 158.9 | 182.2 | |
| XYLD | 2016 | 104.0 | 3.2 | 107.1 | 107.1 |
| 2017 | 114.9 | 5.9 | 124.0 | 124.6 | |
| 2018 | 101.3 | 7.2 | 117.6 | 117.5 | |
| 2019 | 115.8 | 6.7 | 138.7 | 142.1 | |
| 2020 | 106.0 | 8.4 | 137.4 | 140.5 | |
| 2021 | 115.4 | 10.5 | 157.3 | 166.8 | |
| 2022 | 89.9 | 12.1 | 143.9 | 147.5 | |
| 2023 | 90.1 | 9.5 | 153.5 | 163.3 | |
| 2024 | 95.7 | 11.1 | 170.2 | 193.5 | |
| 2025 | 84.5 | 3.3 | 162.2 | 177.4 |
一括投資シミュレーションの解説
もし10年前にQYLDまたはXYLDに100万円をまとめて投資していたら、資産はどうなっていたでしょうか?シミュレーション結果を見てみましょう。
- QYLDの場合:
- 10年前に100万円投資した場合、2025年4月時点で、株価の評価額は約66.8万円と、元本を大きく下回っています。
- しかし、これまでに受け取った配当金の累計額は約88.9万円(2016年~2025年4月)に達します。
- 評価額と配当金の累計額を合わせると約155.7万円(計算上のズレあり、表では158.9万円)になります。
- さらに、受け取った配当金をすべて再投資していた場合、評価額は約182.2万円になっていました。
- XYLDの場合:
- 同様に10年前に100万円投資した場合、2025年4月時点で、株価の評価額は約84.5万円と、こちらも元本を下回っています。
- 配当金の累計額は約78.4万円(2016年~2025年4月)です。
- 評価額と配当金の累計額を合わせると約162.9万円(計算上のズレあり、表では162.2万円)になります。
- 配当金を再投資していた場合は、評価額は約177.4万円になっていました。
このシミュレーションからわかる重要な点は、配当金の再投資が長期的なリターン向上に大きく貢献するということです。一方で、株価自体は下落傾向にあるため、配当金を受け取るだけでは元本割れのリスクがあり、配当再投資をしても市場環境によっては資産が大きく減少する可能性があることも示唆しています。
QYLD/XYLDへ10年前から100万円分を毎月積立投資していた場合のシミュレーション
(参考:グラフ内の薄い線は一括投資の場合の推移)
10年間の積立投資シミュレーション結果
| 銘柄 | 年 | 評価額(万円) | 配当額(万円) | 評価額+配当累計額(万円) | 配当再投資評価額(万円) |
|---|---|---|---|---|---|
| QYLD (積立) | 2015 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 2016 | 11.6 | 0.5 | 12.2 | 12.2 | |
| 2017 | 23.7 | 1.5 | 25.8 | 25.9 | |
| 2018 | 30.0 | 3.5 | 35.6 | 35.0 | |
| 2019 | 44.3 | 4.5 | 54.3 | 54.4 | |
| 2020 | 54.1 | 6.8 | 70.9 | 71.2 | |
| 2021 | 63.1 | 10.2 | 90.1 | 89.8 | |
| 2022 | 54.7 | 10.2 | 91.9 | 82.9 | |
| 2023 | 70.4 | 11.8 | 119.3 | 112.9 | |
| 2024 | 84.8 | 16.8 | 150.5 | 146.6 | |
| XYLD (積立) | 2015 | 0.9 | 0.0 | 0.9 | 0.9 |
| 2016 | 12.0 | 0.2 | 12.2 | 12.2 | |
| 2017 | 24.3 | 1.1 | 25.5 | 25.6 | |
| 2018 | 30.9 | 2.0 | 34.1 | 33.8 | |
| 2019 | 46.4 | 2.6 | 52.2 | 52.5 | |
| 2020 | 53.7 | 4.5 | 64.0 | 63.9 | |
| 2021 | 69.5 | 7.0 | 86.9 | 88.0 | |
| 2022 | 63.9 | 10.5 | 91.7 | 87.8 | |
| 2023 | 74.4 | 10.2 | 112.4 | 108.4 | |
| 2024 | 90.0 | 14.7 | 142.7 | 141.1 |
積立投資シミュレーションの解説
次に、10年前に一括で100万円投資するのではなく、10年間かけて毎月少しずつ(合計100万円になるように)積み立てて投資した場合のシミュレーションを見てみましょう。これは「ドルコスト平均法」と呼ばれる投資手法の効果を見るものです。
- QYLD (積立)の場合:
- 10年間で合計100万円を積み立て投資し、配当金を再投資した場合、2024年末には評価額が約146.6万円になるとシミュレーションされています。
- 累計の配当額は約66.8万円になります。
- XYLD (積立)の場合:
- 同様に10年間で合計100万円を積み立て、配当金を再投資した場合、2024年末の評価額は約141.1万円になるとシミュレーションされています。
- 累計の配当額は約52.8万円になります。
積立投資の特徴:
- リスク分散効果: グラフを見ると、積立投資(濃い線)は一括投資(薄い線)に比べて、資産評価額の変動がなだらかになっていることがわかります。これは、購入タイミングを分散することで、高値掴みのリスクを減らす効果(ドルコスト平均法)が働いているためです。
- 最終リターンの比較: ただし、今回のシミュレーション期間(過去10年)においては、最終的なリターンは一括投資の方が高くなる結果となりました。これは、投資初期の株価が比較的安く、その後の配当再投資効果が長期間にわたって効いたためと考えられます。もし投資開始後に株価が下落し続けるような局面であれば、積立投資の方が有利になる可能性もあります。
- 元本割れリスク: 積立投資でも、市場の下落局面(例: 2022年)では、投資元本(その時点までの累計投資額)を下回るリスクは依然として存在します。
積立投資は、時間分散によってリスクを抑えたい初心者の方には有効な手法ですが、必ずしも一括投資より高いリターンが得られるわけではない点は理解しておきましょう。
QYLD/XYLDの将来の株価成長シミュレーション

将来株価シミュレーション(2025年を100とした場合)
| 銘柄 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QYLD | 100.0 | 95.9 | 92.0 | 88.2 | 84.6 | 81.2 | 77.8 | 74.7 | 71.6 | 68.7 | 65.9 |
| XYLD | 100.0 | 97.8 | 95.7 | 93.7 | 91.6 | 89.7 | 87.7 | 85.8 | 84.0 | 82.2 | 80.4 |
将来株価シミュレーションの解説
ここでは、過去の株価の値動き(年率リターン)が今後も続くと仮定した場合、将来の株価がどのように推移するかをシミュレーションした結果を見てみましょう。注意点として、これはあくまで過去のデータに基づく機械的な計算であり、将来を予測するものではありません。
シミュレーション結果:
- もし過去10年の年率株価変動率(配当を含まない)が今後も続くと仮定すると、QYLDもXYLDも株価は下落し続けるという結果になります。
- 100万円投資した場合、10年後の2035年には、QYLDの評価額は約65.9万円に、XYLDの評価額は約80.4万円になるとシミュレーションされています。
- QYLDの方が下落ペースが速いと予測されています。
解釈と注意点:
- このシミュレーションは、QYLDとXYLDの株価が過去において下落傾向にあったことを反映しています。カバードコール戦略の特性上、株価上昇益を放棄するため、これはある程度予想される結果です。
- しかし、将来の株価は、経済情勢、金利動向、市場のボラティリティ、各ETFの構成銘柄の業績など、様々な要因によって変動します。過去のトレンドが未来永劫続くとは限りません。
しかし、これはあくまで過去の成長率が継続した場合のシミュレーションであり、期待のしすぎは禁物です。過去の成長傾向として参考にしておきましょう。
QYLD/XYLDのリスクファクター分析

リスク指標の比較
| 項目 | 説明 | 値(QYLD) | 評価(QYLD) | 値(XYLD) | 評価(XYLD) |
|---|---|---|---|---|---|
| ベータ | 市場全体の動きに対する感応度 | 0.63 | 市場平均より変動が小さい | 0.50 | 市場平均よりさらに変動が小さい |
| 52週ボラティリティ | 過去1年間の価格変動の大きさ | 19.41% | 価格変動が大きい | 15.69% | QYLDよりは変動が小さい |
| シャープレシオ | リスクあたりのリターン効率 | 0.09 | リスク対比のリターンが低い | 0.28 | QYLDよりは効率的だが低い |
| トータルリターン(1年) | 過去1年間のトータルリターン | 4.09% | 低いリターン | 6.14% | QYLDよりは高いが低い |
| 最大ドローダウン | 過去最大の値下がり幅 | -36.22% | 下落リスクが高い | -30.33% | 下落リスクが高い(QYLDよりは低い) |
リスクファクター分析の解説
投資を考える上で、リターンだけでなくリスクを理解することも非常に重要です。ここでは、QYLDとXYLDのリスクに関するいくつかの指標を見てみましょう。
- ベータ (β): 市場全体(例:S&P500)が1%動いたときに、そのETFが何%動くかを示す指標です。1より小さければ市場平均より値動きが穏やか、1より大きければ市場平均より値動きが大きいことを意味します。
- QYLD (0.63)、XYLD (0.50) ともに1を下回っており、市場平均と比べると値動きはマイルドである傾向がわかります。特にXYLDは市場感応度が低いです。
- 52週ボラティリティ: 過去1年間の株価の変動率(標準偏差)です。数値が大きいほど、価格変動が激しかったことを示します。
- QYLD (19.41%)、XYLD (15.69%) ともに、一般的な低リスク資産と比べると高い水準です。ベータ値は低いものの、独自の価格変動リスクは持っていると言えます。
- シャープレシオ: リスク(ボラティリティ)1単位あたり、どれだけのリターン(リスクフリーレートからの超過リターン)を得られたかを示す指標です。数値が高いほど、効率よくリターンを上げていることを意味します。
- QYLD (0.09)、XYLD (0.28) ともに非常に低い数値です。これは、価格変動リスクの割には、リターンが低い(効率が悪い)ことを示唆しています。
- 最大ドローダウン: 過去のある高値から、その後の安値までの最大下落率です。投資期間中に最大でどれくらいの損失を被る可能性があったかを示します。
- QYLD (-36.22%)、XYLD (-30.33%) ともに非常に大きな下落率です。これは、投資タイミングによっては、資産が3割以上も減少する局面があったことを意味し、高い下落リスクを内包していることを示しています。
これらの指標から、QYLDとXYLDは市場平均に対する感応度は低いものの、独自の値動きによるリスクや、大きな下落リスクを抱えており、リスクに見合ったリターンが得られているとは言い難い側面があることがわかります。
QYLD/XYLDの先月の動向と投資戦略
これまでの分析を踏まえ、QYLDとXYLDへの投資戦略について考えてみましょう。
QYLD/XYLDの現状と特徴(再確認)
- 最大の魅力は高い分配金利回りであり、毎月分配金を受け取れる点。
- カバードコール戦略により、株価上昇による利益(キャピタルゲイン)は限定的。
- 株価は長期的に下落傾向にあり、元本割れのリスクが存在する。
- 分配金額は安定的ではなく、市場環境によって変動する(減配リスクあり)。
- リスク指標を見ると、シャープレシオが低く、最大ドローダウンが大きいなど、リスク対比のリターン効率は低い。
投資戦略の考え方
これらの特徴を踏まえると、QYLD/XYLDは以下のような投資家や目的に合致する可能性があります。
インカムゲイン(分配金)重視型:
- 目的: 資産の値上がり(キャピタルゲイン)よりも、定期的なキャッシュフロー(分配金収入)を得ることを最優先する。
- 戦略: ポートフォリオの一部として組み入れ、毎月の分配金を生活費の補填や他の投資への再投資資金として活用する。
- 注意点: 株価下落による資産全体の目減りリスクと、分配金の変動リスクを十分に理解し、許容できる範囲で行う。
高配当ポートフォリオのアクセントとして:
- 目的: すでに他の高配当株やETFでポートフォリオを組んでいるが、さらに高い利回りを追求したい場合に、サテライト(補助的)として少額組み入れる。
- 戦略: コアとなる安定的な配当株・ETFを中心に据えつつ、QYLD/XYLDで利回りの上乗せを狙う。ただし、組み入れ比率は低めに抑え、リスクを管理する。
QYLDとXYLDの使い分け:
- より高い分配金利回りを求めるなら → QYLD: ただし、ナスダック100連動のため、ハイテク株への依存度が高く、ボラティリティや下落リスクもXYLDより高い傾向。
- 少しでも分散を効かせたい、値動きをマイルドにしたいなら → XYLD: S&P500連動のため、QYLDよりは分散されており、ベータ値やボラティリティも低い傾向。ただし、それでもリスクは高い。
避けるべき投資戦略
- 長期的な資産形成のコア(中心)とする: 株価上昇が期待しにくいため、長期的なキャピタルゲインを狙う目的には不向き。
- 分配金だけで生活設計を立てる: 分配金は変動するため、安定収入源として過度に依存するのは危険。
- リスク許容度の低い初心者: 高い分配金利回りは魅力的だが、その裏にあるリスク(株価下落、分配金変動)を理解せずに投資するのは避けるべき。
結論として、QYLD/XYLDは非常に特徴の強いETFであり、投資する際にはそのメリット・デメリットを十分に理解する必要があります。 インカムゲインを重視する特定のニーズには合致する可能性がありますが、万人向けの投資対象とは言えません。
まとめ:QYLD/XYLDへの投資判断のポイント
QYLDとXYLDは、カバードコール戦略を用いることで非常に高い分配金利回りを実現しているETFです。毎月分配金が支払われるため、定期的なキャッシュフローを重視する投資家にとっては魅力的に映るでしょう。特に、QYLDはナスダック100、XYLDはS&P500を対象としており、それぞれ特徴が異なります。
しかし、その高い分配金の裏側には注意すべき点が多くあります。株価上昇の恩恵を受けにくく、長期的には株価が下落する傾向が見られます。また、分配金の額も安定しておらず、市場環境によっては減配されるリスクも常に存在します。リスク指標を見ても、価格変動リスクや下落リスクは決して低くなく、リスクに見合ったリターンが得られているとは言い難い側面も指摘されています。
したがって、QYLD/XYLDへの投資は、これらのリスクを十分に理解し、あくまでポートフォリオの一部として、インカムゲインを得る目的で活用するのが現実的でしょう。長期的な資産形成の主軸とするには不向きであり、特に投資初心者の方は、その特性をよく理解した上で、慎重に投資判断を行うことをお勧めします。ご自身の投資目標やリスク許容度と照らし合わせ、最適な選択をしてください。
QYLD_XYLDの投資判断で重要なポイント
QYLDの投資判断で重要なポイントと総合評価:
配当利回り:常に10%を超える非常に高い利回りが最大の魅力。毎月のキャッシュフロー重視派には魅力的。
安定性(株価):ナスダック100を対象とするカバードコール戦略のため、株価上昇の恩恵を受けられず、長期的に株価が下落する傾向が強い。特に近年のハイテク株下落の影響を大きく受けている。
成長性(キャピタルゲイン):カバードコール戦略の特性上、株価上昇による利益はほぼ期待できない。
リスク:株価下落リスク、分配金変動(減配)リスクが高い。テクノロジーセクターへの集中度が高く、セクターリスクも大きい。最大ドローダウンも大きい。
分散投資:ナスダック100構成銘柄への投資だが、テクノロジーセクターへの偏りが非常に大きい。
適した投資家:分配金利回りを最優先し、株価下落や分配金変動のリスクを十分に理解・許容できる、インカムゲイン特化型の投資家。ポートフォリオのサテライト的な位置づけ推奨。
XYLDの投資判断で重要なポイントと総合評価:
配当利回り:QYLDよりは低い傾向だが、それでも非常に高い利回り水準を維持している。
安定性(株価):S&P500を対象とするカバードコール戦略のため、こちらも株価上昇の恩恵は限定的で、長期的な株価下落傾向がある。ただし、QYLDよりは値動きがマイルドな傾向。
成長性(キャピタルゲイン):カバードコール戦略のため、キャピタルゲインは期待しにくい。
リスク:株価下落リスク、分配金変動リスクは依然として高い。ただし、QYLDよりは分散が効いているため、セクターリスクは相対的に低い。最大ドローダウンもQYLDよりは小さい傾向。
分散投資:S&P500構成銘柄へ投資するため、QYLDよりは幅広いセクターに分散されている。
適した投資家:高い分配金利回りを求めつつ、QYLDよりは分散性や値動きのマイルドさを重視したい投資家。こちらもインカムゲイン目的で、リスク許容度が必要。


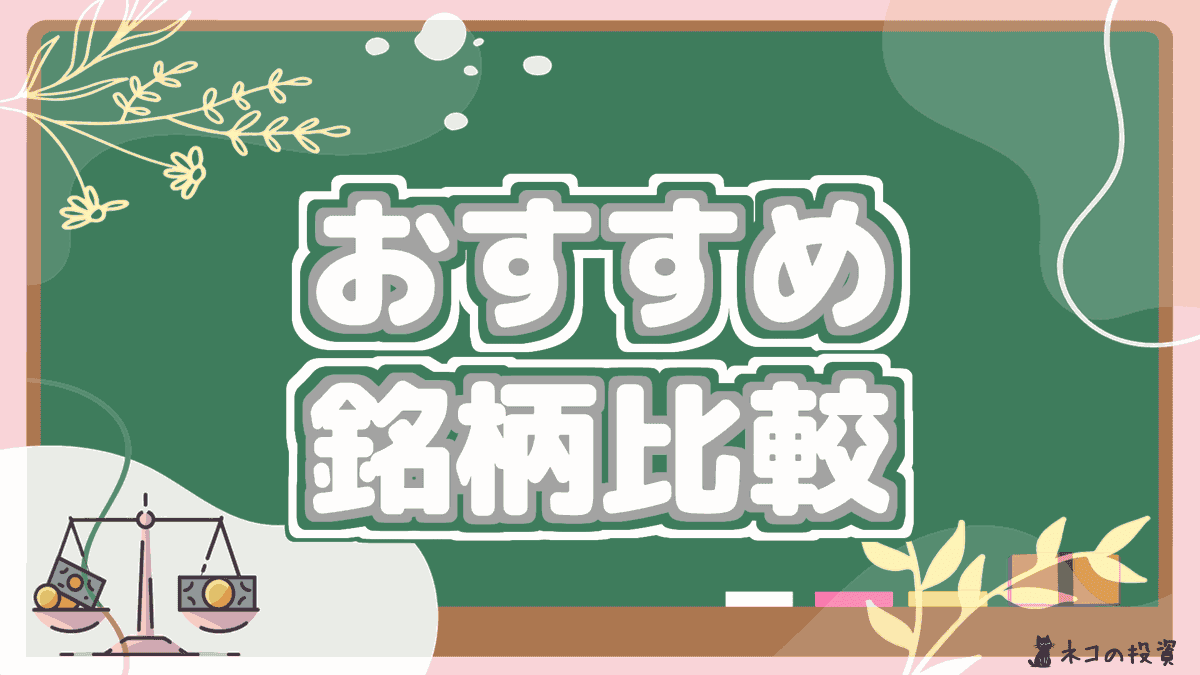






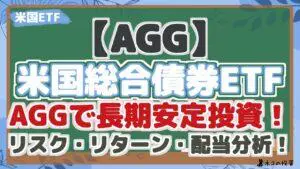












コメント